不登校になった子の中には家庭内暴力を繰り返し起こしてしまう子もいます。
時計や鉛筆削りなどを思いっきり投げられた・・・
実際に殴られて怪我をした・・・
何か言うと暴言で怒鳴ってくる・・・
これらは私のカウンセリングルームに来られるお母さんから聞いたエピソードです。
あまりにも暴力がひどかったために、警察を呼ぶ羽目になったり、毎日びくびくしながら過ごしていたお母さんもおられました。
「命が危ないと思って、夜包丁を隠さないと寝られませんでした」と仰るケースも少なくありません。
ただ、私のカウンセリングを受けた方で数ヶ月ほど経つと、驚くほど子どもが落ち着くようになります。
「普通の会話ができるようになった」と喜ぶお母さんも少なくありません。
お母さんやお父さんがあることを学べるようになれば、一気に家庭内暴力は改善できるようになります。
そのポイントについてお話をしたいと思います。
不登校になる一番の理由
まず、不登校になる一番の理由ですが、それは子どもが学校に合わないためです。
それを私は不登校の3つの原因からお話しています。
3つの原因をわかりやすく学べるメールセミナーはこちらから。
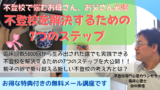
そして、学校に合わない学校に対して子どもたちは一生懸命自分を殺して頑張って登校し続けます。
そうした状態で疲弊してしまい、エネルギーが消耗してしまい、結果として学校に行けなくなります。
よく不登校初期の症状として腹痛や頭痛が起こりますが、それはエネルギーが消耗したサインとして捉えていただけたらと思います。

家庭内暴力を引き起こす理由とは
子どもが不登校になるということはそれなりの理由があるということ。
そして、その分無理をして頑張り続けたということです。
しかし、多くの大人は、「学校へ行くのが普通でしょ」という価値観で考えてしまうため、そうした子どもたちの苦しみが全くイメージができません。
そんな大人の無理解の中で、子どもはどんどんとイライラを募らせていきます。
「なんでわかてくれないの?本当の私はもっと苦しんでいるのに」
そして、不登校になったときに、親は「なぜ学校に行かないんだ」と叱ります。
学校に行かせることが親としての義務だからです。
しかし、子どもは「なんでわかってくれないんだ。こんだけ辛いのに」と思ってしまい、怒りを爆発させます。
これが不登校の子が家庭内暴力を起こすメカニズムです。
特に自分らしさが出てくる小学校5年生くらいか怒りが暴力化してくる傾向にありますが、大体中1~2くらいで一気に噴出してくるようなイメージです。
力づくの解決法が一番ダメ
子どもが家庭内で暴れたり、暴力を振るったり、「〇ね!!」と暴言を言ってきたとき、一番選択されやすい解決法が、力づくの方法です。
最初は親も負けずに言い返したり、お互い手を出すなんてこともあります。
そうなると怒りがエスカレートし、暴力はますますヒートアップします。
これは大事なことですが、
年を重ねるごとに子どもの力ははどんどん強くなります。
一方で親はどんどん力が弱まってきます。
いつかは力ではかなわなくなってくるのです。
大抵は親が力づくで押さえることをあきらめると、子どもの暴力は弱まってくる傾向がありますが、それでも子どもの中には親への怒りや憎しみが減ることはありません。
そのため、親が何か言うたびに、にらんできたり、無視したり、暴言を言ってきたりします。
親も何も言えなくなってしまうのです。
そして、子どもはずっとゲームをして過ごし、親は腫物のように扱い、その状態がずっと続くと言ったことがあります。

憎しみの連鎖から家族を救うには?
こうした状況が何年も続いてしまって、親も「こんな子産むんじゃなかった」と泣き続けることもあります。
そうした親に対して、子どもは「俺の前で泣くんじゃねえ」とさらに言葉の暴力を浴びせ続けてきます。
完全に憎しみの渦に巻き込まれているかのようです。
こうした状態から抜け出すために、お母さん、お父さんにぜひ取り組んでほしいことがあります。
それは、「子ども本来の姿をしっかりと理解し直していく」と言う作業です。
不登校の子は非常に繊細な一面があり、周りの気持ちを察知して合わせてしまう傾向があります。
それが幼少期から続くので、大人も親も「この子はこんな子なんだ」と誤解してしまうのです。
不登校の子は自分を偽って生きているのですが、心のどこかで「本当の自分はこうなんだよ」とご両親に知ってほしいという思いがあります。
でも、子ども本来の姿が見えなかったばかりに、「この子は私が言っていることは素直に聞いてくれる子なんだ」と子どもに合わない関わり方を続けてきました。
この積み重ねが家庭内暴力の一番の原因なのです。
だからこそ、まずは「実はこの子って本当はこんな子なんだ」ということを知る作業が必要なのです。
子どもを理解すればするほど関係は良くなっていく
ここで大事な視点として、親子関係がよくなっていないのに、アレコレ言っても上手く行くことはほとんどないということ。
選択理論心理学を提唱したウィリアム・グラッサーは
「親子関係が悪ければ、何をしても効果はない」と言っています。
家庭内暴力とは親子関係が悪化している時に起こる事象です。
逆に言えば、親子関係がよくなっていくことが家庭内暴力を改善するための一番の解決方法となります。
そのためには、親が子どもの性格や生きづらさと言う視点から、子どものことを理解していくということが必要となります。
ちなみに、不登校の子どもたちの傾向として「理解してほしい子どもが多い」と言うのがあります。
「あ、お母さん、わかってくれる」なと言う雰囲気が伝わってくると、子どもは少しずつ心を開いていきます。

なぜ、親だけのカウンセリングで家庭内暴力が改善できるのか
私のカウンセリングでは、親が子どもを理解していくという「3つのいく(育)」の一番目を重要視しています。
それは関係を良くしたいのであれば、「相手を理解すること」が一番重要だと考えているからです。
例えば、旅行に行きたいときに、旅先のことが理解できなければ、安定して楽しく過ごすことは出来ません。
たまたまよかった場合もあれば、目的地が休みだったりして最悪の旅行になることもあります。
だからこそ、相手をしっかりと知ること、理解することが関係を良くするための第一歩なのです。
カウンセリングではその「理解」に重点を置いているので、無理なく子どもと関係を良くするための関わり方を見つけていくことができるようになります。
その結果、家庭内暴力が改善され、以前よりも親子関係がよくなり、そして子ども自らが「学校に行く」「フリースクールに行く」「進学する」と未来に向けて動けるようになってくるのです。

まとめ
今回は家庭内暴力についてお話をさせて頂きました。
家庭内暴力は子どもが頑張って周りに理解されないまま頑張ってきたことで、その苦しさが恨みや怒りとなって表れてきたものです。
だからこそ、まずはその子らしさ、この子はどういう子だったのかを理解していくプロセスが必要となってきます。
まずはお母さん、いったん深呼吸をしてその子らしさを見つめ直してみませんか?
そこに解決の糸口が必ずあるのです。




コメント