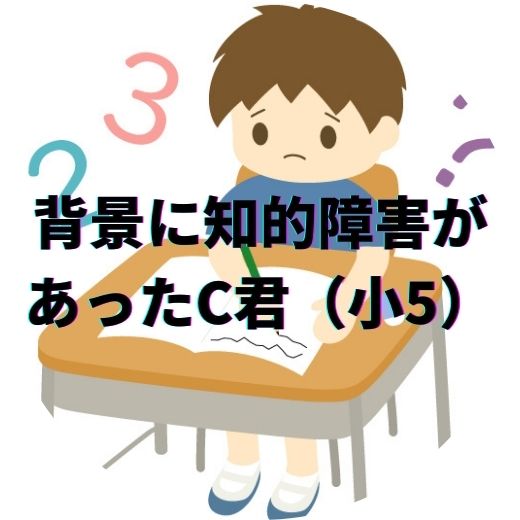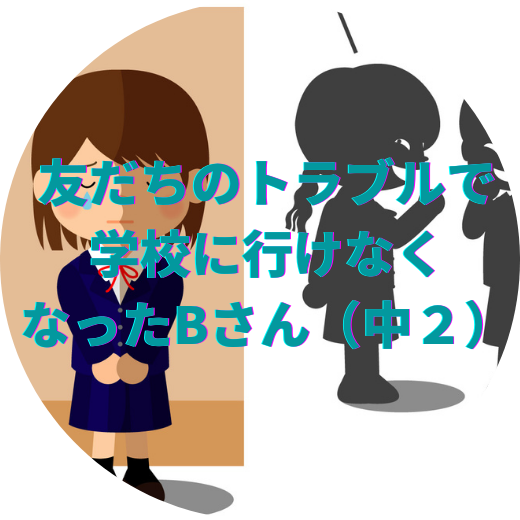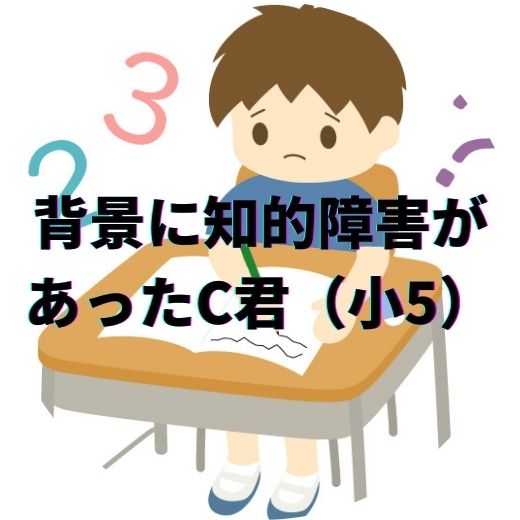当ルームで出会う不登校の事例についてお話しています。
C君が学校に行かなくなるまでの様子
C君は小学校1年生の頃から、字や計算を覚えるのが遅く、先生の言葉も耳に入っていなことが多かったです。
先生も頑張って居残り授業などをして、ようやく1年の終わりごろにはひらがなやカタカナ、足し算はわかるようになりましたが、漢字は少ししか覚えられませんでした。
学校側もお母さんに「一度医療機関に受診した方がいいのでは?」と打診しますが、お母さんは自分の育て方が否定されたと受け取ってしまい、学校と大喧嘩をしてしまいます。
確かに、C君は覚えたり、理解するのが遅かったりしていましたし、3歳時検診でも言葉の遅れなどを指摘されたこともありました。
また、C君は一つのことに拘ってしまうと、そこから抜けることができない特性も持っていました。
ただ、世話好きの女の子がC君のお世話をしてくれたり、クラス自体が落ち着いていたので、それほど気になることは少なかったようです。
小学校4年生の時、運動会の直前に急に学校に行かなくなりました。
当時は無理やり泣き叫ぶC君を無理やり車の中に入れて連れていくこともありました。
しかし、校門の前に来ると、体が固まり、パニック状態になります。
校門の前から動こうとしないのです。
お父さんもお母さんも段々と諦めていくようになっていきました。
不登校になった後の様子
不登校になった後は、家で過ごすことが多く、ゲームなどをして過ごしました。
先生が来くると会うことはでき、お話をすることもできます。
でも学校や勉強の話になると、「うん」「うん」とうなずくだけで、「明日行こうか」と言うと「わかった」と言います。
でも次の日になり、お母さんが声掛けをすると固まってしまい、やはり学校に行くことは出来ません。
ちなみに、家ではお母さんに過度に甘えるようになったりするようになりました。
また、お母さんが「これをして」と頼んでもしないことも増えてきました。
イライラしたお母さんが「早くして」と怒ると、びっくりして頼まれごとをします。
段々と怒らないとしないようになり、お母さんも段々とC君に対していら立ちが止まらなくなりました。
お母さんはお父さんに対してもイライラするようになり、過程の雰囲気も悪くなってきます。
それと同時に、C君はますますゲームに没頭するようになってきました。
なぜ行けなくなったのか
そんな時に、お父さんとお母さんは当ルームの支援に来るようになりました。
私が最初に聞いたこと、引っ掛かったことは、過去に勉強での遅れが顕著であったことや、発達の遅れを指摘され続けてきたことです。
実際にC君に会ってみると、見かけは普通の子でしたが、こちらの言うことに対して話を聞いていないというか、理解力の乏しさを感じました。
私の中で知的障害が背景にあるのではないかという疑いが出てきました。
おそらく、C君は他の子と比べて学校の勉強に対して特別な支援が必要なお子さんである可能性は高いです。
小3までは他の子とそれほど大差がないので、何とかクラスの雰囲気にもついて行くことができます。
しかし、小4になると段々と他の子との成長の差が大きくなり、学校で躓くようになります。
具体的には会話が合わない、先生の指示が難しくなる、勉強が一気に難しくなる。
一般的には9歳、10歳の壁と呼ばれており、普通の子でもいったん躓くと学校が一気にしんどくなってしまうことがあります。
C君の場合は知的なハンディキャップもあり、その躓きが大きく、またそれに加えて人と自分との違いを感じやすい傾向を持っていたのだと推察されます。
「なんでみんなできるんだろう」「なんで僕だけ怒られるんだろう」
そうした思いの中、先生や周りに言われるがまま頑張り続けてしまい、ある日「もう無理」と体が反応し、不登校の状態になったのだと考えられます。
一言付け加えて置きますが、知的障害が不登校の原因ではありません。
知的なハンディキャップは学校の中でしんどさにつながるものの、それが不登校の直接の原因にはなりません。
実際、知的なハンディキャップを持ちながら、勉強について行けないまま学校に行き続けている子は結構多いのです。
C君の場合は、それに加えて不登校特有の繊細さや生きる力の弱さが背景にあったものと考えられます。

考えられる手立て
さて、ここでお父さん、お母さんに「C君は知的障害です」とは言えません。
理由は、知的障害かどうかを決めるのは医師の仕事であり、それがないうちは臨床心理士であろうと言ってはいけないからです。
また、安易に言うことで、お母さんやお父さんが混乱してしまい、かえってC君に悪影響を与えてしまう可能性もあります。
この時に第一に考えるべきことは、C君が「将来どういう風に生きていけるようになってもらいたいか」ということ。
「できれば笑顔でC君らしく生き生きと頑張れるお子さんになってほしい」とお父さん、お母さんも思っているはずです。
まずはその辺りを丁寧に聞いていきます。
すると、お母さんの中でC君が他の子よりも成長が遅かったというエピソードがたくさん話されました。最初の方でお伝えした話は、この辺りで出てきました。
そこで私は子のように伝えます。
「となると、C君は前と同じような感じで学校に行かせるよりも、何かC君に会ったような環境があるといいですよね」
お母さん、お父さんも大きくうなずきます。
そこで私はそうしたお子さんに対して、学校でもその子に合った教育を提供していたり、またC君に合った学びを提供してくれる場所もあることを伝えます。
お母さんは「そういうところがあるんですか?」と興味を持ってくれます。
私は「ただ、こうした場所に行くとなると、条件があるんです」と返します。
「なんでしょうか?」とお母さん。
ここで私はC君に対して、医療機関でまずは検査を受けてみるように勧めました。
医療機関に行けば、知能検査や性格検査をしてくれるので、C君の状態が客観的にわかる可能性があります。
また、医師が診断書を書けば、放課後等デイサービスなどの行政サービスを受けることもできます。
まず学校に戻るというよりも、学校以外の場で何らかの活動を通して自信を持たせることが第一選択だと考えました。
どういった病院がいいかわからない場合は、保健所に相談に行くと教えてくれます。
お母さんもここまで来ると、自分のプライドではなく「C君の未来のために」という親としての思いで動いてくれるようになりました。
ちなみに、医療機関で検査を受けたところ、やはりと言いますかIQは60程度でした。
医学的には知的障害の範疇に入ります。
しかし、おかげでC君はまずは放課後等デイサービスの支援を受けることができるようになりました。
2時間の個別療育特化型のところに行きました。
そこでは丁寧に勉強を見てもらうことができ、「わかりやすい」とC君は嬉しそうに通うことができました。
その1年後に児童相談所に行き、療育手帳の取得もできるようになりました。
税金なども免除されたことで、大分経済的なゆとりもできるようになってきました。
その間に学校への復帰もできるようになってきています。
C君のその後
C君は6年生の中頃から保健室登校を介して別室登校を開始しました。
先生が個別に教えてくれたこともあり、また好きな工作などもさせてもらえたこともあり、とても楽しんで過ごせたようです。
この辺りになると、お父さん、お母さんも「C君にはC君に合ったやり方や生き方があるんだ」と考えるようになってきました。
残念ながら年度途中であったため、特別支援学級への編入はできませんでした。
また、クラスの子に対して「何を言われるかわからない」と怖がっていたため、教室に戻ることはありませんでした。
ただ、ここまで来るとお父さんもたくさん障害者就労などの勉強をしてきており、C君にも「こういう風な仕事もあるよ」「こういうところで働けるよ」といろんなことを教えていました。
C君もお父さんやお母さんとの関係が良くなっていたのと、もともとの素直さもあって、「こういうところもあるんだ」と目を輝かせています。
そこで、ご両親はこうC君に聞きます。
「中学校は学校の勉強をするのと、働く勉強するのとどっちがいい?」
C君は「働く勉強したい」と言います。
そこでC君は中学校は特別支援学校に行きました。
特別支援学校が他の学校と違うのは、障害者就労をしていくための授業があるということです。
見学に行くと、C君は「ここに行きたい」と言い、中学は特別支援学校に進学することにしました。
実はC君のような子でも特別支援学校に行く子はたくさんいます。
中には不登校だった子もいるくらいです。
理想としては、そこで障害年金を取りながら、障害者就労をすることで、C君に合った自立の仕方が見つかるようになるといいのではないかと思います。
お父さん、お母さんもC君を通して
「人の生き方って、本当にそれぞれあるんだと思いました。
自分の考えが正しいとは限らないとC君を通して学ばせていただきました」
と話していました。