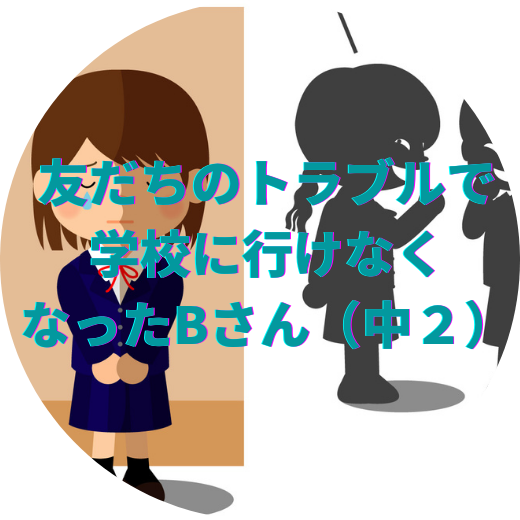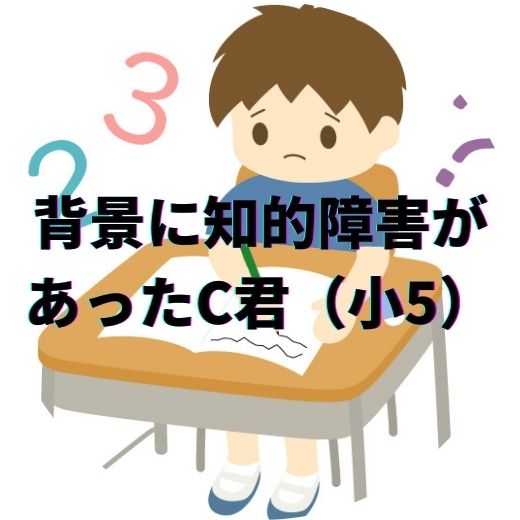当ルームで出会う不登校の事例についてお話しています。
Bさんが学校に行かなくなるまでの様子
Bさんは中学校になってから急に「学校に行けない」と言うようになった子です。
中学校に入り、ある女子グループに入りました。
理由はみんな吹奏楽部に所属していたからです。
Bさんも吹奏楽部に入っていました。
そのグループにはボス的な子がいて、その子が中心となってイベントを提案したりしていました。
結構、エネルギッシュな子だったようで、部活でも一年生ながら主導権を持っていたようです。
しかし、どういうワケかBさんはそのグループの雰囲気に合いませんでした。
当時の担任の先生の話では、「おとなしくて目立たなかった子」だったそうです。
10月に入ると、文化祭で練習も忙しくなっていきます。
Bさんは3年生の先輩に教えられながらパーカッションを担当しました。
その先輩とは相性も良く、「すごいよ」とほめながら教えてくれるので、Bさんも熱心に取り組んでいました。
やがてその先輩も文化祭と同時に引退しました。
そこから、同学年たちの子からいろいろと言われるようになります。
所属していた女子グループの子から「ちょっと、ちゃんとやってよ」と度々叱られるようになりました。
Bさんはもともと褒められて頑張れるタイプの子で、先ほどの先輩は「すごいじゃない、ここ注意して叩けるようなったんだ」と度々Bさんの良いところを伝えてくれたそうです。
この先輩、かなりすごいですね。
人を育てる職業に向いているんじゃないかと思います。
ただ、それと同じことが他の子ができるとは限らないわけで、もともと人よりも覚えるのに時間がかるタイプのBさんに対して、周りからの風当たりがきつかったのです。
「私が悪いから責められているんだろう」
そう思って必死に練習しますが、どんどんタイミングやリズムは狂ってくるし、自分でも全く上手にできません。
3学期に入ると、学校に行こうとすると吐き気が出るようになり、トイレにうずくまることも多々ありました。
心配したお母さんが内科に連れて行き、「逆流性食道炎」と診断されます。
1月の終わりごろから全く学校に行けなくなりました。
不登校になった後の様子
不登校になった後は、しばらくはベッドに横たわる日々が続きました。
1週間ほど経つと、ベッドに横になってゴロゴロと漫画を読んだりして過ごします。
それを見かねたお母さんが「そんなに暇なら学校に行ったら?」と言うと、Aさんは急に顔がこわばってしまい、固まってしまいます。
また、当時のお母さんには、なぜ学校に行かないのか、さっぱりわからない状態です。
Bさんが何も言わず、ただ身体的な不調を訴えているからです。
その頃、心配した友達のお母さんから、Bさんがどうやら吹奏楽部でいじめのようなものにあっていたらしいと聞かされました。
お母さんはすぐに学校に電話して、学校側も事実確認をしました。
顧問の先生や担任の聞き取りによって、上述のBさんが学校に行けなくなる前の様子がわかってきたのです。
ただ、いじめという程ではないけれども、周りがBさんに対してきつく当たってしまい、それで不登校になったということを学校側は女子グループと話し合いました。
そして女子グループも「言い過ぎたかもしれません。辛くさせてしまってごめんなさい」といった内容の手紙をお母さん経由でBさんに渡しました。
しかし、Bさんは絶対に読もうとはしません。
もちろん、学校に行こうともしません。
「あの子たちも反省しているし、意固地にならないでそろそろ学校に戻ったら?」
と言うとBさんはすごい剣幕で
「何もわかっていないのに偉そうに言わないで!!」
とお母さんに言いました。
初めてのことでお母さんもびっくりしました。
結局、その後は別室登校も行かず、中2になっても学校に行けない日々を過ごしています。
なぜ行けなくなったのか
そんな中で、中2の8月ごろにお母さんとお父さんが、当ルームにやってきました。
ご両親が来るということは、相当家族の中で困っていたんだろうと思います。
開口一番、「いじめで学校にいけなくなって」とお母さんが言います。
そこで私は「いじめや人間関係は不登校の原因じゃないですよ」と伝えました。
お母さんとお父さんは「え?」と反応します。
確かに経緯を見ると、いじめや人間関係が原因であるかのように見えますが、本当の原因はBさんが本来自信を持てないタイプの性格だったこと(こういうタイプには褒めることが一番効果的です)、そのために周りからいろいろ言われてしまうとつぶれやすい傾向があったことです。
おそらく本来は、じっくり時間を掛けて取り組むことでうまくいくタイプです。
ちなみに、所属していたグループの子たちは感覚的に「これがいい」と思ったらすぐに行動に移すことができるタイプのようでした。
そうなると、Bさん自身、そのグループになじめなかったのもわかります。
もしかすると美術部や文学部のようなところが合っていた子なのかもしれません。
ちなみに、吹奏楽部に入った理由をお母さんに聞くと、「友達に誘われたから」でした。
なるほど、と思いました。
このように、Bさんの場合は人間関係そのものと言うよりも、合わない環境の中でそれを跳ね返すだけの力がなかったことが一番の原因です。
そして、なぜ合わないかと言うと、体育会系のようにハキハキとしたところよりも、自分のペースを尊重してくれるようなところで良さを発揮できるタイプのお子さんだということです。
その中でBさんもかなり頑張ったんだろうと思います。
「もう駄目だ!!」とストレスが体に出てくるまで。
まずはお父さん、お母さんにはBさんのことを改めて知ってもらうことが第一歩になります。

考えられる手立て
カウンセリングを通して、お父さん、お母さんも大分Bさんのことが理解できるようになってきました。
しかし、このままでいいワケはありません。
かといって、Bさんを無理やりどこかに連れていくことは出来ません。
そのため、最初のステップとして、Bさんを理解してもらうことから始め、少しずつ関係を作り直すことから始めました。
この場合、どういうことから始めるかと言うと、Bさんになり切って考えてもらうという方法があります。
例えば、Bさんがどういう風に学校の中で過ごしていたのか、それがBさんにとってどれほど苦しかったものかを、お母さん、お父さんにイメージしてもらうのです。
なぜ、この方法をとるかと言うと、頭だけで理解しても意味がないからです。
大切なのは、心の底から理解できるかどうかです。
感覚的に「あ、ここまで苦しい中、頑張ったんだ」と理解できるようになると、自ずとBさんは心を開いてくれる可能性があります。
そして、お父さん、お母さんには「選択理論心理学」をカウンセリングの中でお伝えしました。
この心理学で一番好きな言葉で、「過去と他人は変えられない。変えられるのは自分自身だけ」と言うのがあります。
お父さん、お母さんには、まずはBさんを変えようとせず、Bさんに対して「何ができるか」を考えていくことです。
ただし、「できること」がBさんの思いの沿ったものであることが大切です。
そのための話の聞き方もお伝えしました。
サポートをして1ヶ月頃になると、Bさんはお父さんやお母さんと会話ができるようになり、休日にお父さんと遠方ですが車で買い物に出かけるなどの変化が見られるようになりました。
しかし、お母さんの方は不安な表情を見せます。
聴くと「子どもの気持ちが理解して、確かに関係が良くなったが、果たしてこのままでいいのでしょうか?」と不安を口にします。
また、学校や別室に行かないBさんに対して、「イライラや怒りで心が一杯になる」ともお母さん自身の気持も話されました。
この気持ちや親として当然のものです。
ただ、こうした気持ちはすぐに子どもに伝染してしまいます。
事実、お母さんがこうした気持ちになると、Bさんは決まって不機嫌になったり、お母さんに対して悪態をつく様子も見らるようになります。
不登校のお子さんの特徴として、周りの雰囲気を察知する力に優れているということ。
なので、お母さんの気持ちはわかるものの、まずは学校に行くよりも子どもとの関係を築いていくことをゴールにしていくことです。
子どもが安心して前を向けるような関わり方が意識できるよう特にお母さんを中心にサポートしていきました。
Bさんのその後
Bさんは中3まで結局は行きませんでした。
しかし、家族との関係が再構築されたのと、お母さん自身がBさんとの関わり方を学んできた為、将来の進路について話をすることができるようになりました。
Bさんの気持ちを尊重しながら、話をしっかりと聴いてきました。
Bさんは「声優の仕事がしてみたい」と話します。
このとき初めて将来の夢を語ってくれました。
多分、馬鹿にされると思って口に出すのをためらっていたのでしょう。
勇気を振り絞ってお母さんに話し出しました。
これを聞いて以前のお母さんであれば「そんな夢みたいなことを言って」と聴かなかったでしょう。
でも、「あなたの人生だから大丈夫だけど、どうやってなるのか考えはあるの?」と冷静に返しました。
Bさんは「わからない」と答えます。
そこで、お母さんは「じゃあ、どうしたらなれるのか探してみて」と話し、「もし難しかったらお母さんも一緒に手伝うよ」と伝えます。
その後、Bさんは自分で探して、やはり高校は行った方がいい、また専門学校はお金がかかるし、卒業してもお金を払ってスタジオで練習をしないといけないなど、声優になるためのいろんな情報を集めてきます。
そこでBさんが出した結論は、「単位制の高校に進学して、バイトでお金を貯めながら高校卒業資格を取って、専門学校に行く」というものでした。
正直、ここまではっきり言える子はなかなかいません。
お父さん、お母さんは「わかった」と答えました。
その後、Bさんは単位制高校に進学し、バイトも頑張っています。
同級生と会うのが怖いので、バイトは倉庫関係で働いていますが、親切なおばちゃんもいて楽しく行けているようです。
また、今の単位制は不登校の子も受け入れているところも多く、その中で仲の良い友だちもできました。
最初は学校やバイトはしんどかったですが、今は人にも恵まれているようで、楽しそうに過ごしているようです。
最近になって、「人と話をする練習のためにも、接客の仕事もしてみたい」と話すようになりました。
一番変わったのはお母さん自身で、最初の頃と比べて随分と丸くなった印象を受けました。
「今までは娘を変えることばかりにこだわっていました。
それじゃダメなんだと娘との関りを通して気づきました。
それよりも自分にできることに意識を向けた方がいいんだと娘との関りを通して、わかってきました。」
と、話してくれます。
私たちは自分中心で考えてしまうと、そこからうまくいかないときに不安や心配事が増えてしまい、人間関係が悪化してしまうことがあります。
「娘は娘、自分は自分」と割り切って、Bさんの頑張りを応援していくような関わり方ができたことで、Bさんも安心して「自分らしい頑張り方」を見つけていくことができたんじゃないかと思います。